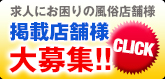365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第1話退屈な雨(前編)-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第1話】退屈な雨(前編)
構内では落雷による電車の遅れや運転の見合わせを知らせるアナウンスがしきりに流れている。抑揚のない声が「お忙しい中大変申し訳ございません」と繰り返した。
早めに会社をあがったが、すでに電車は止まり、バスとタクシーには長蛇の列ができていた。駅前の喫茶店は帰宅難民で溢れかえっている。会社から駅までの数百メートルを歩いただけで、足もとがぐずぐずになって不愉快だった。携帯電話に向かってどなり声をあげている中年男性の声が聞こえる。執拗な湿気が改札前の疲れた会社員たちを神経質にさせていた。
金曜なのについてないな、と思う。別に何の予定もないけど。平日でも週末でも、予定があってもなくても、毎日退屈なことに変わりはなかった。最近は誰といても何をしてもつまらない。
ずぶ濡れのサラリーマンが、視界に飛び込んできた。
その男はひどく息を切らしていた。振り返って雨空を見上げ、今自分がこの中を走ってきたのが信じられないといった具合に「うわー…」と小さく声をあげた。さらに運転見合わせの表示を見て「ええー」と苦笑した。男の前髪から滴が絶え間なく垂れている。
その様子がなんだかおかしかったし、帰れなくなった者同士の不思議な連帯感もあって、カバンの中のミニタオルを男に差し出した。
男はビックリしてしばらく目を泳がせたが、すぐ伏し目がちになって「すみません、ありがとうございます」とタオルを受け取った。
「あ…顔ふいちゃっていいですか?」
「あ、どうぞ」
「すみません、洗って返します」
「いえ、気にしないで使って下さい」
電光掲示板を眺めながら、ポツリポツリと会話した。雨が少し弱まってきたので、そろそろ電車も動き出すだろう。男は、いつも必ずカバンの奥に入れておくはずの折りたたみ傘を今日に限って忘れてしまったのだと言った。
「ほんと、今日はついてねえなあ」
男がかすれた声で呟く。反射的に、
「もし時間あったら、今から飲みに行きませんか」
と言ってしまった。男は声を出さず、顔だけでビックリした。
「え、いいですけど、いいんですか」
「どうせしばらく帰れないし暇だしと思って…すみません、変なこと言って」
「あっいえ、僕は全然大丈夫です。何にも予定ないんで。こんなずぶ濡れが相手でよかったら…」
男が照れ臭そうに笑う。さっき苦笑いした時もそう感じたけど、やっぱり「この人なんか素敵だな」と思った。
唐突に訪れた非日常に、興奮している自分に気付いた。
今日はきっとついてる、と思った。
駅前の安いバーは、帰宅を諦めて開き直った人たちで溢れかえっていた。
フロアの立ち飲み席で乾杯してから、遅い自己紹介をした。男は27歳のエンジニアだという。自分は不動産会社の経理をしていると言った。
「すみません、急に無理なお誘いしてしまって」
「いや、ほんとに暇だったんです。むしろありがたいです」
男の白いシャツがまだ湿っている。雨に濡れた髪が間接照明を浴びて艶々していた。
普段よりも酒のペースが早くなり、初対面の男相手に普段誰にも言わないような愚痴まで打ち明けた。無愛想なせいで会社の人たちから陰で「能面ちゃん」と呼ばれているのだと言うと、男は爆笑した。男は深刻な顔をしないしリアクションが大きいので話しやすかった。
気がつけばだいぶ時間が経っていて、妙に開放的な気持ちになっていた。目の前の男にもっと近づきたかった。
どさくさにまぎれて小さなテーブルの下で手を握る。男は一瞬気まずそうに視線を外したが、静かに手を握り返してきた。指先で手の甲をなぞると、ピクと反応があって、やがて指を絡め合った。
普段なら、絶対こんなことしないのに。知らない男にタオルを差し出したり、飲みに誘ったり、手を握ったり、今日は少し変だ。でも身体の芯がジンジンして止められない。大きな目をキョロキョロさせて困惑する男は、年上なのにひどく可愛らしく見えたし、もっとドギマギさせたかった。
店の外に出ると、雨があがって雲間からわずかに星が見えた。生ぬるい風が心地よい。腕を絡めるようにして手をつなぎ、人通りの少ない路地の陰でキスを求めた。男の息が荒く舌の動きが激しくなる。まだ少し湿った服の上から身体を指でなぞり、股間へと手を滑り込ませると、男は「おわっ、ちょ…っ」っと情けない声をあげた。
「すごい…こんなに硬くなってる」
服の上から手で上下にこすると、男は苦しそうに小さく呻いた。もたれていた雑居ビルの脇のドアをあけると、非常階段へと続いているようだった。男を招き入れ、再び激しく舌を絡ませた。キスしながら、ズボンのチャックを下げて下着の切れ込みに手を突っ込み、怒張したペニスを引っ張り出す。狭い場所から解放されたペニスが勢いよく上を向いた。
「人が、来たら…」
男は息も絶え絶えに言ったが、制する手に力が入っていなかった。
何故こんな大胆なことをしているのか、自分でもわからない。しかし、男が吐息を漏らすたびに、身体が熱くなって我慢できなかった。
飛び出したペニスに夢中でしゃぶりついた。その時、はっきりとり「楽しい」と感じた。
本当はずっとこういうことがしたかったのかもしれなかった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)