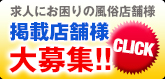365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第41話「カウンター」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第41話】「カウンター」前編
「斉藤さん、いつ私とセックスしてくれるの?」
エマさんが、酔った目を潤ませてカウンター越しに僕の顔を覗き込んだ。からかっているだけだとわかっていても、ついその唇に引き込まれそうになる。
小さなバーやスナックが並ぶ雑居ビルの細く急な階段を上がると、5人座れば満席になってしまう小さなバーがある。店員はカウンターにひとりしかおらず、毎日日替わり。ヒゲ面のアーティスト風の男がシェイカーを振る日もあれば、若くて好奇心旺盛な女の子が話し相手になる日もある。
エマさんは、毎週火曜日のカウンターを担当している熟女だ。いつもヘラヘラ酔っぱらっていて、営業中に寝てしまうことがたびたびある。しかし、泥酔客やしつこい客を軽くいなして帰らせるのがうまく、ああ見えて昔は銀座のクラブでブイブイ言わせていたらしいと、常連客の一人が噂していた。
彼女のゆるい魅力にひかれ、僕は火曜日に通うようになった。エマさんは、僕の顔を見るたびに「斉藤さん、筆下ろしさせて」とからかうのがお約束だった。
その日は珍しく、日付の変わる0時前から客足が途絶え、閉店間際には店内は僕とエマさんだけになってしまった。
「もうお店閉めちゃうね。斉藤さん、まだ飲んでてもいいよ」
エマさんは看板を取り込み、よろよろと閉店準備を始めた。カウンターの中を片付けて売上をまとめ、空の酒瓶を店の外に出すと、ガチャリと鍵を閉めてしまった。
「え、僕もう帰りますよ!」
「いいじゃん、もうちょっとゆっくりしていきなよ」
そう言うと、エマさんは僕の膝の上に対面して座り、首に両手を回した。
「ちょっとどこ座ってんですか!」
僕の張りつめた股間に、自分の股間を押しつける。彼女の内腿は熱く、スーツ越しにその温もりと重みが伝わった。いつもカウンター越しに見る彼女の厚い唇がすぐ目の前にあった。
エマさんは「セクキャバごっこ」と言ってゲラゲラ笑った。
「からかうのもいい加減にして下さい。僕だって一応男なんですよ!」
思っていた以上に、鋭い声が出てしまった。こんなに密着されると、いつもの冗談を受け入れる余裕すらなくなってしまう。
「ごめん、こういうことされるの嫌いだった?」
エマさんは素直に謝った。しかし、まだ膝の上だ。
「嫌いなわけじゃないけど…」
「けど?」
「触りたくなるから、やめて欲しいです…」
恥ずかしくて視線をそらしたが、エマさんが優しく微笑んでいるのがわかる。
「私は、斉藤さんに触ってもらいたいと思ってるの」
そう言って、エマさんは僕の両手をとり、自分の胸に押し当てた。
形のいいおっぱいが、手の中に収まる。柔らかくて温かい。両手でゆっくり揉みしだくうちに、僕の股間はさらに固くなり、エマさんの恥骨を刺激した。
「い、いいんですかこんな…」
「いいの、もっとちゃんと触って」
と、自分でカットソーをまくし上げ、ブラジャーのホックを外した。目の前に現れた生のおっぱいを、おそるおそる揉んだりつまんだりしていたが、薄茶色の乳首が立ってきたのをみて、思わずしゃぶりついてしまった。
「あぁっ…ん」
エマさんのあえぎ声は、いつものハスキーな声と違って甘く可愛らしかった。唾液を多く使い、じゅる、じゅるるっとわざと音をたてる。
「あ…ん、気持ちよくなっちゃう」
乳首を甘噛みすると、「くぅ…っん」と吐息を漏らし、腰をくねらせた。この体勢だと2人の股間が近すぎて、すでに挿入しているかのような錯覚に陥っていた。
「ね、もう我慢できなくなっちゃった。おちんちん挿れちゃおうか」
エマさんが耳元で囁く。
「え、でもまだなんにも…」
「そんなの、後でゆっくりやればいいよ」
いかにもエマさんらしい返答に、思わず笑ってしまった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)