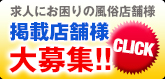365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第33話「隣人」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第33話】「隣人」前編
最近隣の部屋に越してきた男は、いかにもモテそうな風貌で、女をとっかえひっかえしていた。
夜になると、私はベッドの上に座って壁にもたれかかり、隣室からの音を待った。
鍵を差し込む音、ドアが開く音に続いて、複数の足音、話し声、何かを置く音がする。
女たちの声は毎回違う。よく笑う子や低い声で話す子、しゃくりあげて泣く子もいる。
2人の子が同時に来ることもあった。
何もないままく(聞こえないだけで、キスやペッティングくらいはしているかもしれない)帰っていく女ももちろん多い。
しかし、シャワーの音が長く続いたら、彼女たちは30分以内に必ず喘ぎ始める。
お湯の音を合図に、私はいそいそとオナニーの準備を始めるのだった。
ベッドが安物なのか、それともよっぽど激しいセックスをしているのか、スプリングのきしむ音が目立つ。
最後まで小さく「あっ…あっ…」しか言わない子や、悲鳴に近い声をあげる子もいて、喜びの表現はさまざまだ。
「やめて」「もうダメ」「死んじゃう」と止めに入る場合と
「もっと」「そこ、そこ」「奥がいい」と誘導する場合の違いも興味深い。
私は隣の男の激しいピストンを想像しながら自慰をした。
壁に耳をつけ、女の喘ぎ声に合わせてクリトリスをなぞり、指を穴に這わせて出し入れする。
ローターやバイブを使う時もある。広く汗ばんだ背中。乳房にしゃぶりつく唇。激しく打ち付ける腰と尻。低い呻き声。0.03ミリの袋に放出される精子。
そこまで想像して絶頂に達する。
そして、こんなことをしている自分が急に虚しくなり、布団をかぶって寝てしまうのだった。
ベッドの音が聞こえない時も、男に乱暴に犯される妄想でオナニーをした。
ある日曜の午後、隣室は珍しく静かだった。ベランダで洗濯物を干していると、チャイムが鳴った。
ドアの穴から覗くと、隣人が立っている。
私は強く動揺し、居留守を使おうと思ったが、好奇心を抑えられずにドアを少しだけ開けて顔をのぞかせた。
「はい?」
「302の岡本です」
隣人は柔らかい笑顔で言った。少しだけ無精髭が生えている。
私よりもずっと年下なのは明確だった。近くで見ると、思ったより背が高くて筋肉質だ。
「これ、よかったらどうぞ。実家から送られてきたんですけど、すごい量で」
と、男はゴーヤがたくさん詰まった紙袋を差し出した。
一瞬、その形状に怯んだが、お礼を言って受け取った。
「それで、あの、うち、友達が遊びに来ること多くて。音とかうるさくないですか」
「いえ、全然大丈夫ですよ」
私は満面の笑みを作った。
うるさいことはうるさいが、それをオカズにしているので何の問題もなかった。
「それならよかったです。あと、よかったらこれも使って下さい」
そう言って差し出したのは、太くて長い真っ黒なバイブだった。
私は衝撃で体が凍りついた。その隙に隣人は半開きだったドアをこじ開け、室内に入って鍵を閉めた。
「鈴木さん、いつも壁際でオナニーしてますよね? 音聞こえてますよ」
さっきまでの人懐こい表情は消え、鋭い目つきになっている。
「何言っ…」
とっさに身を引こうとしたが、大きな手が素早く私の両手首を掴み、体を引き寄せて後ろから羽交い締めにした。
「ちょっ、やめて下さい…っ」
隣人は、低い声で私の耳元で囁いた。
「イク時、俺の名前叫んでますよね?」
ドクン、と全身に衝撃が走る。私が彼の動向を盗み聞きしていたように、彼もまた私の声を聞いていたのだ。
「ちが…っ」
「俺のこと想像しながらま●こかき回してるんでしょ? 俺そういうのすごい興奮するんですよ」
「やめて!」
首筋にキスしながら片手で私の両手首を掴み、もう片方の手で乳房をに乱暴に揉みしだいた。
強い力でねじ伏せられ、怖かった。でも…

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)