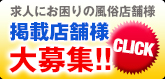365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第30話「女の子願望」エピローグ-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第30話】「女の子願望」エピローグ
誘われるがままに、ベッドに腰をかけた。
再び優しくキスしながら、陰茎を手でしごく。
「クリトリスぐちょぐちょだよ。もう硬くなってきちゃった。すごい淫乱なのね」
「あっあっ、あっ」
甲高い声を抑えることができなかった。
ねばねばになった人差し指と親指を、わざと俺の目の前でつけたり離したりした。
「ほら、こんなにガマン汁がいっぱい出てる。恥ずかしくて興奮しちゃった?
この姿を大勢の人に見られてるって想像しただけで
クリトリスびんびんになってたもんね。変態だもんね」
「変態」という言葉に、カッと顔が熱くなった。
もしかすると、俺はずっとそう言われたかったのかもしれない。
「変態クリ●ンポ、私がもっと気持ちよくしてあげるね」
「はい…」
俺はうわ言のように「気持ちいい…気持ちいい…」と繰り返しながら
いつしか涙目になっていた。
こんな格好をさせられて辱めを受けているのに、反応している自分に絶望した。
そして、それ以上に大きな歓びを感じていた。
◆
◆
◆
騒がしいオフィスに、電話の音や慌ただしくキーを打つ音が響く。
俺の上司は、昼休みがとっくに終わっていてものんびり歯を磨いてから着席する。それを咎める者はいない。
「あ、やだどうしよう、これまだやってなかった」
取引先からの催促のメールが来ていたのか、メールチェックした途端に青ざめていた。
ファイルから必要な書類と資料を取り出し、
「これ、明日朝までに大至急ねー」
と言って、俺の机の上にドンと放り投げた。
最近では「お願い」すら付けなくなった。俺は上司の顔も見ずに
「今それどころじゃないんで、他のチームに回してもらえます?」
と、紙束をつっ返した。彼女は、キョトンとしていた。
「え、急ぎの案件なんだけど」
「リーダーの担当ですよね、ここ。俺、●●の処理で手一杯なんで」
にべもなく断ると、上司はあからさまに不機嫌になってパソコンに向かった。
約束があるとか体調が悪いとか言って、いつも俺に仕事を押し付けて定時で上がってるんだ。
今日ぐらい徹夜で仕事したって問題ないだろう。
ふと、ファイル棚のガラスに映った自分と目が合う。
スーツを着た男ではなく、栗色の髪の美女が映っていた。
珍しく電話で怒られている上司をチラリと盗み見て、思う。
俺はあんたよりずっと美しい、と。
メールの着信音に気付いてスマホのロックを解除する。
あの日、俺に女装させてくれたお姉さんからだった。
「今日、ちゃんと服の下にいやらしい下着つけてきた? 後でじっくり見せてね」
スーツの内ポケットを探るふりをして、中を覗くと白いワイシャツからピンク色のブラジャーが透けている。
誰にも見つからないように、そっと笑みを浮かべた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)