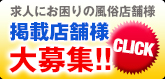365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第24話雷雨 (中編)-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第24話】雷雨 (中編)
磯部は、テーブルの脇に敷かれた布団にもぐりこみ、半分空いたスペースを笑顔でポンポンと叩いた。胸元が少しはだけ、非常用ライトが二つの膨らみの影を色濃くしている。「据え膳食わぬは…」という言葉が頭をよぎり、植村は喉を鳴らした。
せんべい布団に並んで寝ると、体の左側に磯部の体温を感じて熱かった。
「なんか修学旅行みたいですね」
「修学旅行で女子の布団に入ったことないですよ」
アハハと磯部が明るく笑った。磯部さんは、好きな男子の布団にもぐり込んでいたのかな、と植村はふと思った。磯部が胸元に頭を乗せると、シャンプーの匂いが香った。密着した部分の全てが温かく柔らかい。吐息がかかるほど顔を寄せて、磯部は言った。
「キスしていいですか?」
「…磯部さん、酔ってますね」
「そんなことないです。ムラムラしてるだけです」
キスすると、微かにビールの苦みが広がった。舌を絡めているうちに、頭の芯がボーっとしてきて、「本当にいいのだろうか」という迷いが消え去ってしまった。
磯部は植村の耳や首筋に唇を這わせ、乳首を口に含んで舌で包み込んだ。手が浴衣の中に侵入し、脇腹から腰骨にかけて指先でなぞる。柔らかくて切ない刺激に、思わず声が漏れてしまう。いい年したおっさんが、若い女性に攻められて喘ぐなんて情けないと思ったが、植村が声を出せば出すほど、磯部は喜んだ。
「植村さん、可愛い。もっと聞かせて下さい」
「はぁっ…ううっ」
屹立した硬い竿を、ボクサーパンツの上からしごく。亀頭をこねたり手の平でさすったりされると、気持ちよくてじれったくて身体をよじった。
「もうパンツびしょびしょですね。どうして欲しいですか?」
「ふっ…うあぁっ」
「直接触って欲しい?」
植村は、コクコクとうなづく。磯部はおもむろに自分のパンティを下し、シックスナインの体勢で植村の顔の上にまたがった。
「私のことも気持ち良くしてくれたらいいですよ」
磯部の卑猥な肉弁が丸見えになっていた。毛は少なく、濡れそぼった秘孔がヒクヒクと欲しがっているのがわかった。柔らかな肉に唇を押しあて、夢中で酸味がかった蜜を吸った。
「ああっ…いいっ、植村さん、気持ちいいですっ」
喘ぎながら、ボクサーパンツに手をかける。勢いよくブルンと飛び出した男根を、愛おしそうに手でしごいた。
「うぅっ、あっ…」
「あぁん、パンパンになってて、やらしい…」
「んんっ、んっ、うぅっ」
磯部は陰茎を奥まで咥えこんだ。温かな舌がうごめいて、筋にまとわりつく。カリの周りを舐め回すと、植村の内腿がビクビクと反応した。互いの粘膜を舐め合う音が、暗い部屋に響いた。
磯部は、植村の唇が好きな場所にあたるように腰を動かした。その動きが小刻みになり、絶頂が近付いているとわかった。ついには陰茎から口を離してしまった。
「あっ、あっ、やだ、もういくっ、いくっ、私、いっちゃう…っ!」
声にならない声をあげ、磯部は2・3度身体を震わせた。「ふふ、すぐいっちゃった…」
恥ずかしそうに笑うと、磯部は顔面から退き、植村の口の周りにべっとりとついた自らの愛液を舐め取った。
そのまま首、脇、乳首、へそ、脇腹へと移動 し、再びいきり立った秘茎へと舌を這わせた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)