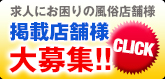365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第32話「陰と陽」後編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第32話】「陰と陽」後編
「ゆうべのこと、ほんとに覚えてないの?」
「は、はい…すみません」
「別人みたいだったよ。エロくってさあ、自分から腰ふっちゃって」
「嘘です、そんな…」
「今だって、自分で触ろうとしてるじゃない」
股間に伸ばしかけた手を掴まれ、ハッとした。こんなこと、人前でしたことないのに。
まだ酔っているのだろうか。
大島課長は、私の手を自分の熱く膨張したものにあてた。
「えっ、すご…」
硬い、と言おうとして唇を塞がれた。
課長はゆっくり舌を絡ませながら私の濡れた陰肉を指で優しく撫でた。
「濡れやすいんだね、もうビショビショになってる」
「んん…っ、あっ…気持ちいい…です」
「ゆうべも前戯してないのにいきなりヌルッと入っちゃったしね」
「えっ」
「え、じゃないよ。君が俺の上に乗ったんじゃない。全然覚えてないんだなあ」
すみません、と再び謝ろうとしたが、課長の指がゆかるみの中に侵入して言葉を失った。
内側の、一番好きな部分を擦られて、内腿に力が入る。
「あっあっ、そこ…そこすごく好きです」
「すごいな、中からどんどん溢れてくるよ。ここそんな気持ちいい?」
「いいです…っ! あっ、これ以上…気持ち良くしたら、すぐイッちゃいますっ」
課長は「いいよ、何回でも」と微笑み、指の速さや力加減を変えずに同じペースで刺激し続けた。
「あっ、あっ、イクっ、イキそうですっ」
一瞬、大島課長の目に不思議な光が灯り、顔が真剣になった。私の手の中の陰茎がより膨らむのが分かった。
「あっ、ああー…っ! イクっイクっイクっ!!」
汗がドッと吹き出て、足の先がピンと伸びた。波が引くまで、体が何度か大きく痙攣した。
課長の鈴口から大量のガマン汁が垂れて、私の手のひらがヌルヌルになっている。
私は股をはしたなく広げると、いったばかりの濡れそぼった肉襞を自ら指で開いておねだりをした。
「大島さん…早く、早くここに挿入て下さい…っ」
大島課長の顔からいつのまにか余裕が消え、無言でゴムを装着した。
しばらくピタピタと亀頭を擦り付けてから、一気に挿入した。
「はあっ…ん!」
課長の怒張した陰茎は長く凶暴で、動くたびに子宮口にガツガツと当たるのがわかる。
「牧野ちゃん、ごめん、俺なんか我慢できなさそう。すぐイっちゃうかも」
「ダメッ!! まだイっちゃダメです」
「牧野ちゃんがいけないんだよ、こんなエロい身体してるから」
課長は私の身体を裏返した。
バックから再び激しくピストンされ、私は狂ったように喜びの声を上げた。
「もっと!もっと突いてぇっ!」
片手を後ろに引っ張られ、上体を起こすと目の前の鏡台に映った自分が、まるで別人のように感じられた。
髪を振り乱し、たわわな乳房を上下に揺らし、欲望のままに腰を振る淫乱がそこにいる。
昨晩課長を襲ったのは、この女だと思った。
「気持ちいい…っ、中が、中がすごい熱くなってきた…っ」
「イっていいよ、牧野ちゃん、イって」
「ああっ、熱いっ…イクっ、イっちゃう!」
「ううっ…」
「…っ」
大島課長はしばらく後ろから私を抱きしめ、繋がったまま荒く息を吐いていた。
やがてズルリと陰茎を引き抜き、ゴムの口をしばった。
「牧野ちゃん、すごいな…。全部搾り取られるかと思ったよ」
私は、寝そべったまま愛液でベタベタに濡れた課長の陰毛を撫で、空っぽになった2つの玉を優しく揉んだ。
「いやいや、さすがにもう無理だからね」
たじろぐ大島課長に、今度は私が微笑みかける。
地味で内気な事務員の私は、もうどこにもいなかった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)