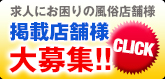365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第64話「押入れ」中編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第64話】「押入れ」中編
私が高校に入ると、兄は家に彼女を連れてくるようになった。
何人か違う女の子を見かけたので、どうやらそこそこモテるようだ。
私は無関心を装っていたが、あの部屋で兄がセックスしていると考えるだけで、
足の間の小さな芽が膨らむのがわかった。
その頃、私は男の体に興味津々だった。
エロ本だけでなく、家のパソコンでエロ動画も見ていたし、
風呂上がりの兄をチラチラと盗み見たりしていた。
兄は、小学校から高校まで野球で鍛えていて、たくましく引き締まった体をしている。
私も、いつかあんな体の男と裸で抱き合うのだろうかと妄想しては、毎日悶々としていた。
その日も、家族が誰もいない時間帯を狙い、兄の部屋に忍び込んだ。
押入れの下段に潜り、本棚の裏に手を伸ばす。
四つん這いのまま後ろ向きで戻ろうとした時、階段をあがる足音が聞こえた。
押入れの中にいたせいで、玄関のドアを開ける音に気がつかなかったのだ。
今慌てて飛び出したら、兄の部屋から出た瞬間を目撃されてしまう。
全身から嫌な汗がドッと吹き出した。
どうする? なんて言い訳する? と頭を巡らせていたが、
兄と女性のが聞こえた瞬間、目の前がまっくらになって体が動かなくなってしまった。
「こないだのあれ、どうだった?」
「あー、大変だったよ、あの後。竹内がさあ…」
兄と彼女は、部屋に入ってからも、くつろいだ様子で世間話を続けた。
私は、押入れの中で息を潜め、体を縮こまらせていた。
緊張のあまり、全身が冷たくなっている。
ステレオから音楽が流れ始めたが、取り留めのない会話は途切れることがなかった。
二人はだいぶ仲がいいようだ。
「早く帰って欲しい」
「部屋から出て行って欲しい」
という気持ちと、
「どうせやるなら早く始めて欲しい」
という両極端な気持ちがせめぎあっていた。
どのくらい時間が経ったのか、皆目わからなかった。
押入れの中は、数分が数時間に感じられた。
やがて、ベッドのスプリングがきしむ音と共に、不自然な沈黙が訪れた。
「あ…妹さんに聞こえちゃう…」
「音立てなければ大丈夫だよ」
やん…ダメだって」
兄を制する彼女の声に、緊張感はなかった。
共犯者たちがクスクス笑っている声が聞こえる。
「はぁ…っ、んんっ…」
やがて、ピチャ…ピチャ…という体液の音が聞こえ始めた。
「あ、やあっ…そんな音たてないで…」
「いつもよりすげー濡れてる。興奮しちゃった?」
「や…あん、恥ずかしい…」
「うちの妹、隣の部屋で聞き耳立ててるかもよ」
「ふふ、やだ…あんっ」
残念ながら、妹は隣の部屋ではなく同じ室内にいた。
私は、音を立てないように細心の注意を払いながら、そろそろと自分のスカートに手を伸ばした。
すぐ近くで、男のゴツゴツした手が、柔らかな肉を撫でている。
女の生々しい喘ぎ声が聞こえる。
私は、興奮でどうにかなってしまいそうだった。
「ああー、やばい…どんどんよくなっちゃう…」
「あーすげえ気持ちよさそう、もっと顔見せて」
「や、だめえ…そこ、弱いとこだから…っ」
「いいじゃん、いきなよ」
「あ、あ、だめ…、声、声…っ我慢できないから…っ」
「大丈夫、大きい声だしていいよ」
「だめ、ほんとだめ…! や、あっ、あっあっっ」
「深雪ちゃん、いって、我慢しないで」
「あーっ、んんっ…い、いっ、い…っっ!!」
声を押し殺したのか、手で口を押さえたのか、絶頂の瞬間の声は聞き取れなかった。
彼女の声に合わせて、パンツの上から肉襞の間を擦った。
愛液が溢れ、押入れの床に垂れてしまいそうだった。
「見つかったら取り返しのつかないことになる」とわかっているのに、
手を止めることができなかった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)