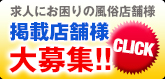365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第68話「レッスン1」-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第68話】「レッスン1」
「沢田さん」
彼が、私の名を呼ぶだけで、子宮がキュッと収縮するのがわかる。
「緊張してます?」
小刻みにコクコクとうなづいたが、河本君は表情をかえずに、
「大丈夫ですよ、ただの練習なんで。リラックスして下さい」
と、こともなげに言う。
君が相手だから、緊張してるのに。そんなこと言えるはずもなかった。
◆-----◆-----◆-----◆
河本君は、以前飲み会で知り合った1つ年下の友達で、ゴシップ誌の編集者として働いている。彼から流れてくるフェイスブックの記事はいかがわしいものばかりだ。興味津々で読みはするものの、いいね! はなかなか押せなかった。
特にイケメンというわけでもないのに、彼はよくモテる。無愛想で一見冷たそうに見えるのだが、案外人懐こく、よく笑う。様々なジャンルの本を読んでいて、知識も豊富だった。「性豪」と噂されていて、実際に彼とセックスしたことある女の子たちは「すごかった」「よかった」と口を揃えたように称賛していた。
彼なら、私の悩みも引かずに聞いてくれるかもしれない。そう思い立ち、「久々に飲みませんか」とDMを送ると、即「いつにします?」と返信が来た。
「沢田さんから連絡くるなんて、びっくりしましたよ」
待ち合わせの居酒屋に現れた河本君は、身体が引き締まり、頬がこけて目がギョロギョロしていた。前会った時より、髭が伸びて男らしくなっていたが、素っ気ないのに意外と笑い上戸なところは、相変わらずだ。
近況を報告し合ったり共通の友人の話などをして、お酒がほどよく回ってきたのを見計らい、本題を切り出した。
「河本君、あのね、折り入ってお願いがあるんだけど」
「なんでしょう」
「あの、嫌じゃなかったら、一回だけでいいんで、私とセックスしてもらえないかな」
「え」
声をあげて驚くでも、怪訝な顔をするでもなく、河本君は「大胆っすね」と笑った。
「ごめん、こんなこと相談できるの、君くらいしかいなくて。君としたなんて、誰にも言わないし、乗り気じゃなかったら断ってくれて全然かまわないし、途中で帰ってもいいから!」
「ずいぶん切実ですねえ」
ジョッキをテーブルに置いてから、彼は静かに言った。
「何かあったんですか」
私は、事の経緯を説明した。昨年彼氏に振られて以来、自信を喪失しっぱなしなのだ。
元彼とは、学生時代から丸7年付き合った。2年くらい前から、よそよそしさを感じるようになったが、長く一緒にいればそういうものなのだろうと楽観していたし、このまま結婚するものと思っていた。
唐突に別れを切り出され、その理由を問い詰めると、最初は「仕事に集中したいから」「支えていける自信ないから」とそれらしいことを言っていたが、最終的に彼が放った言葉は、
「それに、ほら、俺たち、あんまり体の相性も、アレだったし」
だったのだ。
「この人、7年間ずっと気持ちよくなかったし、それを我慢してたんだ! って、すごいショックで」
「うーん」と、河本君は眉をひそめた。
「AV観て真似したり、それなりに頑張ってたつもりだったんだけど、やっぱり全然駄目だったみたい。初体験も彼とだったし、1人しか知らないから、他の人に比べたらよっぽど下手なんだろうなって」
よかれと思ってやっていたことも、彼にとっては退屈でしかなかったのだと考えるだけで、申し訳なさと虚しさで体がバラバラになりそうだった。しばらくは、男の人を見るのさえ嫌だった。
「また同じこと言われるかもって思うと、怖くて誰とも付き合えなくなっちゃったの。だから、一回上手い人に一から教えてもらえないかと思って…」
返事はなかった。
河本君は、不機嫌な顔のまま腕を組んで黙り込んでしまった。
「ごめんね、変な話して。そんなん言われても困っちゃうよね」
「あ、いえ、ちがうんです。今からだとどこのホテルがいいかなと思って」
伝票を持って立ち上がる彼を、見上げる。
「え、いいの?」
「困ってる人はほっとけないタチなんですよ」
河本君は、困ったように笑った。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)