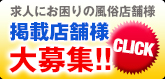365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第36話「蛙」後編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第36話】「蛙」後編
吉田を起こすと、なぜ南さんがいるのか分からずにキョトンとしていたが、やがて自分が呼び出したことを思い出し、何度も謝っていた。駅まで3人で歩き、私鉄の改札口で吉田と別れた。
僕はさっきのショックが抜け切れず、ずっと上の空だった。
吉田の姿が見えなくなると、南さんが僕の手をそっと握った。
「ホテル行きましょうか?」
その目の中に再び小さな光が宿ったのを見た。うなずくしかなかった。
南さんは僕の手を引き、古くて小さなラブホテルへ入った。その足取りに迷いはなく、だいぶ慣れているようだった。部屋に入るなり、南さんは僕を壁に押し付けてベルトを外し、ズボンとパンツを下ろしていきなりしゃぶりついた。
「はあっ、金原さんのおちんちん、すごく大きいんですね…」
生まれて初めて感じる口内の温かさや舌の柔らかさに、すぐさま精子が先端までせり上がった。
「や、南さんっ、やめ、出ちゃう、出ちゃうから!」
「いいの、最初はお口に出して」
「はああっ」
我慢する余地もないまま、破裂するように精子をぶちまけてしまった。南さんはそれらを受け止め、さらに尿口に残っている精子も吸い取り、うっとりとした表情で口内に広がる白濁液の味を楽しんでいた。目をつむって飲み干すと、潤んだ目で微笑んだ。
「ふふ、いっぱい出ちゃいましたね」
「す、すみません」
「その代わりたくさんしてね?」
南さんはスルスルと服を脱いだ。全体的にむっちりしていて、おっぱいも想像より迫力があった。乳輪は大きく、肌との境目がわからないくらい色素が薄い。手にあり余る乳房を揉んでいるうちに、再び欲望が込み上がるのを感じた。
「あん、すごい…もうコチコチになってる。今度は私のことも気持ちよくして下さい」
ベッドに寝かせられ、南さんは僕の顔の上にまたがった。
「とろとろのおまんこを開いて、私の恥ずかしいところ見て」
初めて間近で見る女性器は、本当にここに挿れていいのかと不安になるほど小さかった。灰色の皮膚を広げると、ハッとするほど鮮やかなピンクの粘膜が現れ、ぽっかりと空いた穴から愛液がとめどなく溢れていた。舌先でちろちろと舐めると、南さんが大陰唇を僕の顔に押し付けた。
「ああっ、もっと、もっと舐めて!」
むせ返るような匂いも気にせず、僕は夢中で舐めたり吸ったり舌を伸ばしたりした。
「ああっ、感じちゃう金原さん、すごく上手、んんっ」
再び僕の陰茎を舌と唇で包み込み、首の捻りを入れながら激しく上下に運動した。
「あっ、南さん、ごめんなさい、俺また出ちゃいます、あっあっ」
「んっ、んんんっ!」
南さんの大臀筋が激しく震えた。それと同時に、僕は再び大量に放射してしまった。しばらくひくひくと痙攣したままでいたが、南さんはゆっくりと態勢を整えた。
2発目の精子は飲み込まずに、ティッシュの中に出した。南さんはティッシュの箱の横にあるコンドームを取ると、少し硬度を失った陰茎にかぶせた。
「まだ大丈夫ですよね?」
そう言って、上から腰を下ろし、膣の中に陰茎をズブズブと少しずつ沈めていった。
「はあっ…ううっやばい、これ、中すげー熱い」
「あっ、あっ中でまた膨らんでるぅ…。おまんこに上からズボズボ犯されるの、どう? 気持ちいい?」
「はあっ…ああっすごい気持ちいいです」
「ああーっ私もこの角度すごいいいの…っ、金原さんのおちんちん奥まで届いて気持ちいいっ」
南さんは腰を激しく動かし、粘液にまみれた肉と肉を擦り付けた。
「あ、あっ、駄目です、そんなに動いたら、出ちゃうんで!」
「ダメっ、まだ我慢して! もっとグリグリしてえ…っ」
「あーーほんとやばいです、出る、出るっ」
「ああんっい、いいっ、いいっ、あっあああっ」
「っああっ!!」
その日、僕は朝までに合計5回射精してしまった。
「今度は、吉田さんも一緒に3人でしましょうね」
南さんの目の奥が赤く光る。僕はボンヤリした頭の中で、男の精子を搾り取る悪魔のことを思い出していた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)