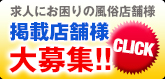365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第55話「鍋」中編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第55話】「鍋」中編
塩崎先輩の乳輪は、乳輪がほとんどなく、乳房の真ん中で唐突に突起していた。乳房の大きさとは不釣り合いなほど大きい。今までいろんな男たちに吸われたり噛まれたりして、肥大してしまったのだろう。
「菅原、ボーッとしてないでもっと近くに来いよ。お前、塩崎とやったことないんだろ?」
返事しようとしたが、喉がカラカラになっていてうまく声がでなかった。
「竹内は常連だもんな。すげえ巨根らしいぜ」
「普通っすよ」と竹内君はビールを飲みながら謙遜した。目の前に半裸の女性がいるというのに、落ち着いたものだ。勝手に、竹内君は童貞仲間だと思っていたので、ショックだった。
太田先輩は、塩崎先輩を抱き起こし後ろから羽交い締めにした。
「こいつ、おっぱいめちゃくちゃ感じやすいから舐めてあげてよ」
「やだあ、恥ずかしいよお」
「お前いつも集団で犯されてみたいって言ってるじゃん。ていうか、今日そのためにわざわざ家に3人集めたんじゃないの?」
「ちがうもん…」
図星だったらしく、塩崎先輩は顔を真っ赤にして俯いた。
「もうめちゃくちゃ濡れてんじゃん。やっぱこうされるって期待してたんだろ? いつも頭の中ちんぽのことでいっぱいだもんな」
「あぁっ…やぁ、ん」
太田先輩が、ショーツに手を伸ばし耳元で囁く。塩崎先輩は、恥ずかしそうに身をよじらせ、太田先輩の股間に尻をこすりつけた。
「ほら、菅原。こいつもう発情しだしてるから、早く」
促されるまま、ベッドの側に膝まづき、乳房に顔を寄せた。塩崎先輩はだいぶ興奮しているらしく、息が荒く肌がじっとり汗ばんでいる。潤んだ目は、羞恥ではなく期待に溢れていた。
「はぁあっ…ん」
硬く伸びた乳首を口に含むと、塩崎先輩は物欲しそうに下半身をもじもじさせた。
「菅原君…乳首…乳首噛んでえ」
コリコリした突起を歯で挟んで軽く甘噛みしたが、先輩は「もっと強く」と不満そうだ。前歯にグッと力を入れると、喜びの声をあげた。
「あーっ…いいっ…乳首痛くされるの気持ちいいっ…もっとしてぇ」
「うわ、そんなのどこで仕込まれたんだよ、変態じゃん。引くわー」
太田先輩が呆れて笑い、キスしたり首筋を舐めたりしながら、服を脱がせた。最初から羽交い締めにする必要はなかったようだ。
「あぁっ…いいの…乳首立っちゃう…もっと、もっとしてぇ」
俺は夢中で乳首を噛み、もう片方の乳首を指で強くつねった。今まで、こんな要求をしてくる女とセックスしたことがなかったので、訳もわからず無我夢中だった。
さっきまで内股でもじもじしていたくせに、先輩はいつのまにか両足をだらしなく開き、ショーツに指をズブズブとめり込ませていた。
その時、カシャッというシャッター音が響いた。
びっくりして振り返ると、無言で酒を飲んでいた竹内君が、先輩の痴態をスマホのカメラで撮影していた。
「えっ…ちょ…」
勝手に撮られたことを抗議しようとすると、
「大丈夫、すぐ消すから」
と、竹内君が静かに制した。
「塩崎さん、カメラ向けるとめちゃくちゃ喜ぶよ」
見ると、はだけたスカートの中で小さな布がぐしょぐしょに濡れそぼっている。
「撮って…いやらしいとこ全部撮ってえ」
先輩は、自らショーツの横の紐をほどいてしまった。毛深く少し灰色がかった大陰唇の中に、鮮やかな赤い肉裂が見える。分厚い小陰唇を指で開き、カメラに向かって足を広げた。
「私のスケベまんこ、もうこんななの…いつもより気持ちいい…っ」
「うわ、もうマン汁泡立ってるじゃん」
「俺、撮影役やるんで、二人でどうぞ」
カメラを構えた竹内君が静かに言った。案外、進行役の太田先輩よりも彼の方が塩崎先輩とやりまくってるのかもしれない。
「じゃあ、お言葉に甘えて」と、先輩は遠慮もなくズボンを脱いだ。
サイズも太さも普通だが、亀頭だけがやけに大きくツヤツヤしている。カリ高の亀頭の先から、先走り液が小さな水泡を作っていた。
塩崎先輩は、目をつぶり陰茎に顔をこすりつけて臭いを嗅いだ。
「はあっ…おちんちん、硬くて…生臭い…」
太田先輩が出したペニスを、ジュポジュポと、下品な音を立ててしゃぶり始めた。セックス狂いの女が、口をすぼめて喜んでいた。
明るく笑う先輩も恥ずかしがる先輩も、もうここにはいなかった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)