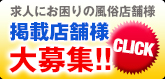365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第49話「オフィス」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第49話】「オフィス」前編
午後9時。無我夢中で進めていた仕事が片付いた。フロアにはもう誰もいない。
書類の印刷が終わるまでの間、一息つこうと自販機に向かう途中、喫煙室に人影を見つけた。
F課長だった。こちらに背を向けて缶コーヒーを飲んでいるようだが、煙草を吸っている気配はない。そもそもF課長は喫煙者ではないはずだ。
おそるおそるドアを開けてみる。喫煙室に入るのは初めてだった。
「あれ、煙草吸うんだっけ?」
私に気づいたF課長が、振り向き様に聞いた。
「こっちの台詞です。何してるんですか」
「ここ、眺めがいいんだよ」
F課長は、いつもぶっきらぼうな話し方をする。人によっては、嫌われていると勘違いしてしまうだろう。本当は、笑い上戸で人懐こいのに、と少し残念に思う。
「こんな綺麗なのに煙草吸う奴しか楽しめないなんてもったいねーじゃん。誰もいない時たまに見てるの」
F課長の傍らに立つと、ガラス張りの窓に光の海が広がっていた。見慣れた風景のつもりだったが、こうして改めて見ると大小さまざまな宝石の粒が夜景を彩り、別の町のように見えた。
夜景を見るふりして、課長の横顔や喉仏をこっそり盗み見する。切れ長の目も神経質そうな顎も、少し伸びた無精髭さえも素敵だと思った。私はこの男の顔が好きなのだ。
先月、F課長とそういうことがあった。その後も肌を重ねたが、社内ではなるべく目を合わせないようにしていた。
ふいに、課長が指を絡ませた。
「…課長、ここ会社ですよ」
「ごめん、なんか夜景見てたらテンションあがっちゃって」
課長が目がクシャッとさせて笑う。
「Mさん、昼間俺のこと避けてるでしょ?」
「だって、なんか恥ずかしいじゃないですか…」
「そう? あんなに恥ずかしいことしといて?」
少し強めに肩を叩いたが、相変わらず目を細めてニヤニヤしていた。笑った時の顔も大好きなのだ。
たまらなくなって、自分から唇を塞いだ。優しく舌を絡ませ合うと、頭がしびれて何も考えられなくなる。
「んっ…んん」
恥ずかしい液が染みだして下着を湿らせているのが自分でもわかった。
「ん、はぁっ、ねえ…課長」
「ここじゃやだ? ホテル行こうか?」
ううん、と私は笑って首をふった。
「一度やってみたかったことがあるんですけど」
「?」
「コピー機の前でしてみたいな」
その途端、課長は勢いよくハハハと爆笑した。
「馬鹿だなぁ、AVの観すぎだろ!」
クシャクシャの笑顔を見て、私もつられて照れ笑いした。
会議室の鍵をしめると、二人は貪るように激しく唇を求め合った。羞恥と罪悪感で不思議な高揚があった。
「そこ、手をついて」
耳元でF課長が囁く。私は会議室のコピーに手をつき、お尻を突き出した。
課長がお尻好きなことは重々承知だ。シスカートをまくり上げ、腰を艶かしく動かす。濡れたクロッチが丸見えになっていると思うと、恥ずかしさで余計に愛液が溢れた。課長は尻肉を両手で撫で回した。
「はぁ…ん」
丸い肉を揉んだり広げたりするだけで、ぬかるんだ秘孔が音を立てる。
「んん……っ」
課長の指がショーツをなぞり、充血した肉芽を優しく撫でる。
「あっ…あっ…そこ…そこもっと触ってぇ」
「ふふ、布の上からでも膨らんでるのわかるよ」
「あっ、あっ、そこクリクリされるの好き…っ、ああっ」
片手で尻肉を揉みながら、片手で肥大した豆を一定のテンポで擦り続ける。
「あーっ、ダメ…それすぐいっちゃう…そこ弱いの、ダメ、いく、いっちゃう、いくっいく…っ!」

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)