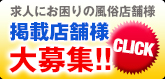365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第61話「スロウ」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第61話】「スロウ」前編
眠りに落ちる寸前の、まどろみの中にいた。
まぶたが重く張り付き、体も動かせない。
ああ、僕はもうすぐ寝るんだなと、なんとなく思う。
ベッドがギシと軋んで、体がわずかに沈む。
誰かがベッドに腰掛けたのだとわかる。その手が頬や髪に触れた。
指先でツウと輪郭をなぞったり、耳の後ろを撫でたり、温かくて気持ちいい。
でも、今は眠くて反応できない。
一瞬、唇に柔らかな感触があった。
「ねえ、まだ寝てるの? もう一回しようよ」
目を半分だけ開けてみると、エマさんが悪魔みたいな笑顔で僕の顔を覗き込んでいるのがわかった。
視界が光の渦に溢れ、痛いくらいだ。
手の甲で目を覆い、背中を向けて寝返りを打つ。
「冷たいな~男っていつもそうだね」
「誰のせいで疲れきってると思ってるんですか」
僕は頭から布団をかぶった。
エマさんは、僕が通う小さなバーで働いている。
美人で、優しくて、いやらしい、年上の女性だ。
閉店後の店内でセックスして以来、僕らはたびたび会っては体を重ねた。
エマさんの部屋に行くことが増えたが、今でもたまに閉店後の店内でセックスしてしまう。
エマさんは酒が入ると淫乱になるタイプで、家に帰るまで我慢できないのだ。
「お酒と男で何度も嫌な思いしたのに、やっぱり大好きだからやめられないんだよね」
ビールをグビグビあおりながら、エマさんは楽しそうに笑っていた。
なんでこんな女好きになっちゃったんだろう、と自分でも思う。
布団をかぶって固く目をつぶる僕の上に、エマさんが覆いかぶさった。
「ねえ、斉藤くん、舐めさせてよー」
と、しつこく駄々をこねる。
少しでも勃起すると、すぐに挿れたがるので、正直クタクタだ。
あまりにもうるさいので「えーい!」と一気に起き上がり、反動でひっくり返ったエマさんを上から抑え込んだ。
「じゃあ、僕のペースでやらせてもらいますよ」
「君のっ…んっ」
口を塞いでゆっくりゆっくりと舌を動かし、丁寧に唇を舐める。
エマさんの唾液を味わうように音を立てて吸いついた。
「ふっ、んん…」
アルコールが入った時みたいに、目の周りがほんのり赤くなり、腰が少し浮いた。
エマさんの発情の合図を見て見ぬ振りをして、僕はしつこく首や鎖骨や脇にキスをする。
「はぁっ、斉藤く…」
髪を撫でたり手を握ったりするだけで、体には触れないよう注意を払う。
エマさんは、何度もキスを求めた。
「んっ…ん、ふぁっ…なんで触ってくれないのぉ」
「エマさんがいつもすぐ挿れちゃうからですよ」
「たまには焦らしますからね」
「やだあ、我慢できないよ」
「でも、僕、エマさんとちゃんと抱き合ってみたいんです」
目を見据え素直に伝えると、エマさんは恥ずかしそうに俯いた。
いつも明るくてわがままなエマさんが、僕よりもずっと年下みたいに見えた。
肌と肌を合わせ、お互いの首、背中、腕、腰、お腹、太ももを撫でる。
たまにささやき合うように会話して、ゆっくりキスをする。
「はぁっ…やああっ」
途中、堪えきれなくなって股間を擦り付けようとしたり、僕の性器に触れようとしたが、その手をそっと掴んで拒んだ。
直接的な刺激は、なるべく避けたかった。
どこを触ると、どんな顔をして、どんな声がでるのか、もっと知りたい。
1時間近く柔らかな愛撫を続けているうちに、エマさんはとうとう涙目になってしまった。
常に濡れやすく、すぐに挿入したがる彼女にとっては生殺しの拷問のようだったに違いない。
「はぁっ、やだあっ…。斉藤くん…お願い、もう、もう挿れて…。あそこがジンジンするのぉ」
頬にキスすると、それだけでビクッと反応するくらい、彼女の体は敏感になっていた。
触らなくても、ズブズブにぬかるんでいることは想像がつく。
僕も、長く焦らし過ぎたせいではちきれそうになっていた。
「待たせてすみません…なるべくゆっくり動きますね」
コンドームをつけ、亀頭の先を充血した肉襞に近づける。
熱がこもっていて、湯気が出そうだ。
ヌチュッヌチュッ、と擦り付けるだけで、エマさんは「ひっ…あぁっ」体を震わせていた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)