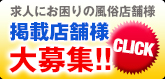365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第43話「家政婦」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第43話】「家政婦」前編
我が家に、家政婦が来ることになった。
母が亡くなって一年半。家の中のことは父と僕で分担していたのだが、最近は二人とも仕事が忙しく、家事に手が回らなくなってきた。結婚した妹や親戚のおばさんに手伝ってもらってばかりいるのも悪いので、それならいっそプロにお願いしてしまおうと、家族会議で決定した。
うちの担当になった渡部さんは、僕と同世代くらいの、ふくよかで綺麗な女性だった。
勝手にお婆ちゃんが来るものと思い込んでいたので、初めてうちに来た時は面食らった。渡部さんは、もう小学生の息子さんがいるのだという。仕事が丁寧で、特に料理の腕前はプロ並みだった。美味しいだけでなく、盛り付けも美しいので父からも好評だった。
たまに早めに家に帰ると、仕事中の渡部さんに会うことがある。ポロシャツに長ズボンという地味なユニフォームを着ているが、テーブルを拭いている時や雑巾掛けの時など、つい彼女の大きなお尻に目がいってしまう。
左右にゆさゆさと揺れるお尻を見ていると、手を伸ばしそうになるが、なんとか堪えている。渡部さんのお尻を思い出して自慰に耽ったことは、一度や二度ではない。
ある日、出張を終えて家に帰ると、玄関に女性用のスニーカーが置いてあった。今日は渡部さんが来る日だったと思い出し、少し浮き足立った。風呂場からシャワーの音がする。
手を洗うついでに風呂場を覗くと、渡部さんが下着姿で風呂掃除をしていた。思わず「うわっ、すみません」と謝り、慌てて顔を引っ込めた。
「えっ!? あっ吉川さん!? ご、ごめんなさい、こんな格好で!」
「いや、すみません、こっちこそ急に!」
渡部さんは、黒いレースのブラとショーツをつけていた。
もう何年も女性の下着姿を見ていなかったので、異常なほど胸が高まった。大きな胸や肉付きのいい腰、ショーツからはみ出たお尻の肉、むっちりした太ももなど、熟女の魅力に溢れていた。
「今日お帰り早かったんですね! 今すぐお茶淹れますから」
「いや、後でいいですから」
僕が制しているにも関わらず、渡部さんは風呂場から出てきた。髪から水が滴れている。
「さっき蛇口を間違えてシャワーの水を頭からかぶっちゃったんです。服を今乾かしてて」
僕は思わず唾を飲み込んだ。
「せ、背中拭きましょうか…」
渡部さんの視線が一瞬僕の目を鋭く捉え、そして柔らかく微笑んだ。
「あら、いいんですか? ありがとうございます」
渡部さんは髪をかき揚げ、うなじを晒した。その様子がたまらなくエロい。バスタオルで首もとから肩、肩甲骨、背中を少しずつ丁寧に拭いて、やがて腰にたどり着いた。
その時にはもう、僕の理性はかなりぐらついていた。ショーツの上からお尻を柔らかく拭く。渡部さんの身体が、わずかにピクリと反応したのを見逃さなかった。
タオル越しにお尻の肉をなぞると、渡部さんは足を少し開き、お尻を僕に突き出した。
「ここも濡れてるので拭いてもらっていいですか…?」
そう言って、お尻の肉を両手で開いた。
恐る恐る、タオルでクロッチの上をなぞると、渡部さんは「はぁっ…ん」と甘い声をあげた。
「あん…もっと拭いて下さい…」
その瞬間、僕の理性は一気に吹き飛んでしまった。渡部さんのショーツを一気に引き下ろすと、大きなお尻に顔を埋めた。
「あんっ、吉川さ…っそんなに吸い付いちゃ…!」
渡部さんは洗面台に手をつき、僕が舐めやすいように、、さらにお尻を突き出した。
「はぁ…ん、舌がヌルヌルして気持ちいい…」

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)