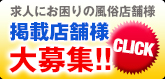365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第23話雷雨 (前編)-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第23話】雷雨 (前編)
風呂から戻った植村は、広い畳の部屋の真ん中に布団が二つ並んでいるのを見て、卒倒しかけた。慌てて、片方の布団を寝室からテレビのある部屋に移動させた。
ライターの植村は、編集者と共に某県の小さな町へ取材に来ていた。その日のT地方は朝から強い風を伴う雨が続いていた。
取材と撮影を終え、満身創痍で駅にたどり着いたものの、改札前に「強風の影響により上下線とも運転を見合わせております」と書かれた立て看板が置かれていた。植村は絶句し、編集者の磯部は「うそぉ」と声を上げた。いつも綺麗にセットされている前髪が乱れ、毛先から水滴が垂れていた。
駅員室に問い合わせたが、山道が通行止めになっているため車も使えないとのことだった。さらに強くなっていく雨を眺め、途方に暮れていると、年老いた駅員が改札の窓から顔を出した。
「そこの旅館に電話してみたら、団体用の部屋が一部屋空いてるって。よかったねえ」
一部屋。植村と磯部は、顔を見合わせた。
廊下から足音がしたので、植村は慌てて座椅子に座り、テレビに集中しているふりをした。
浴衣姿の磯部が、ビールやおつまみの入ったビニール袋を片手に戻ってきた。風呂上がりの髪をまとめ、うなじが出ているせいか妙に色っぽい。
磯部はまだ若いが腕のいい編集者で、いくつもの人気企画や連載を担当している。仕事ができて、明るくて、しかも美人だ。俺のようなしょぼくれたおじさんが同じ部屋にいても、警戒どころか気にもならないのだろう、と植村は思った。
磯部はテレビのある部屋を、植村は寝室を使うことになった。「植村さんも飲みます?」と誘われたが、丁重にお断りした。植村は下戸なのだ。
資料に目を通しているうちに、23時近くになっていた。隣の部屋ではまだテレビをつけているようだったが、ザアッと窓に吹き付ける雨と雷鳴の音が大きすぎて、よく聞こえなかった。仕事を切り上げて、植村は早々と布団に入った。
取材を段取りよく進めていれば、電車が止まる前に帰れたのに。磯部さんに大変なご迷惑をかけてしまった。使えないおっさんだと思われていることだろう。布団の中でネガティブなことを考えるのが、植村の癖だった。自分の情けなさや、一日の疲れがこみ上げ、大きくため息をついた。
その時、窓から強い閃光が射し、地響きと共にドオン! と大きな衝撃音がした。同時に、視界が急に真っ暗になった。隣から「キャッ」と小さな叫び声が聞こえる。植村は布団から飛び起き、目が慣れてから柱に備え付けてあった懐中電灯を手探りで掴んだ。
隣の部屋を照らすと、磯部がビールの缶を片手に縮こまっていた。
「ああ、ビックリしたぁ」
いつも通りの明るい声なので、植村は安心した。
「落ちたみたいですね」
「そうですね。いつ復旧するのかな」
「あ、じゃあこの懐中電灯使って下さい。俺、どうせもう寝るんで」
「ええー。電気が点くまでこっちにいて下さいよ。広い部屋に1人じゃさすがに怖いです」
美人に「ここにいて」とお願いされるなんて、もう一生ないかもしれないと思った。植村は、恐る恐る正面の座椅子に座った。
暗い部屋の中、仕事のことやお互いのことをポツリポツリと話した。磯部が「今日は私がモタモタしたせいでこんなことになってしまって、申し訳ないです」と謝ったので、植村は恐縮してしまった。何度か仕事をしたが、個人的に話をしたのは初めてだった。
途中、旅館の仲居が各部屋に非常時用の小さな照明を配ってくれたおかげで、相手の表情を確認できるくらいの明るさになった。
雷鳴は、いつのまにか遠のいていた。
座椅子の上で体育座りしていた磯部が、膝を抱えてうつらうつらし始めたので、「布団で寝た方がいいですよ」と声をかけた。
「俺、しばらくここにいますから」
「…じゃあ、植村さんも一緒に寝ましょうよ」

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)