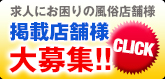365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第56話「鍋」後編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第56話】「鍋」後編
「んっ…んんっ…はぁっ」
「あー…めっちゃ気持ちいいー。すげーもうすっかりスケベ顔になってるじゃん。塩崎ってカメラ向けられると盛り上がるタイプなのな」
太田先輩は、塩崎先輩の後頭部を押さえつけて喉の奥まで挿入し、カメラに向かってピースサインをした。その途端、パックリ開いた膣口から白い愛液が中からドロッと勢いよく流れ出た。相当興奮しているようだ。
「んんっ、おちんちん美味しい…っ、口まんこに精子いっぱい出してぇ」
塩崎先輩は、首を激しく動かし、夢中でペニスに吸いついた。自らの人差し指を中指を出し入れし、もう白目になりかけている。
定期的に聞こえるカメラのシャッター音が、彼女を煽っているようだった。
俺はどうしていいかわからず、ただ乳首を噛んだり乱暴に揉みしだくしかなかった。
「あ、いきそう、ごめん俺先に出すわ」
「ふうっ…んっんぅ…ふぅっ!」
太田先輩が上を向いて小さく「ああー」と喘ぎ声をあげた後、少し遅れて塩崎先輩も身体をビクビクッと震わせた。精子が気管に入ったらしく、しばらくむせていた。
「…っ、はぁっ、すごい濃くて苦い…」
塩崎先輩は、涙目になりながら、喉に残った残滓をうっとりと味わっていた。絶頂の余韻を楽しんでいるのか、それとも俺を挑発しているのか、大股開きのままいやらしく腰をくねらせた。泡立った愛液でぐっしょり濡れた大陰唇が、不思議な匂いを放っている。俺は我慢できなくなり、ついにベルトを外した。
「みんなに見られてると、すごくいい…いつもよりおまんこが疼いて我慢できないのぉ…菅原君、早く、奥…奥のとこ突いてぇ」
撮影役の竹内君がそっとコンドームを差し出した。目の前でエロい女が悶えているというのに、緊張して装着に時間がかかってしまい、焦らす余裕もなく熱い割れ目に挿し込んだ。
「ふ、あっ…きたぁっ…すごい、菅原君、届いてるっ」
「あ、うわ、すっげえトロトロ…」
温かな肉壁が包み込み、肉襞が絡みながらギュッと締めつけてくる。正直、やりまくってる人のものとは思えないくらいの締まり具合だった。正常位なのにグイグイ腰を振り、奥に当てようとしてくる。
「あっ、あっ、いいっ、おちんちん気持ちいいっ…もっと奥ゴツゴツさせてぇ」
「ここ、これですか…っ」
行き止まりの膣口に亀頭の先をグッと押し当てると、体を大きくビクンとさせた。
「ああっ、ひぃい…いいっ」
軽くいってしまったらしく、中がきつくて痛いくらいだった。俺のペニスは意志とは関係なく膨張を続け、破裂しそうだ。
「あ、はぁっ…中でどんどん硬くなってるぅ、やだぁあ、またいくっ…いっちゃう…っ!」
「塩崎先輩…っ、いってくださいっ」
「あっ、あっ、やばい、またいくっいくっ、とまんないっっ…あっはぁっ、ひああ…っ」
「…っ!」
本当はもっとよがらせるつもりだったのに、耐えられず俺も出てしまった。
先輩はとろんとした顔で余韻に浸っていたが、まだまだ物足りないらしく、腰をくねらせている。
撮影役だった竹内君が、とうとう脱ぎ始めた。さっき太田先輩が言ってた通り、かなりの巨根だった。色素が薄くまっすぐ伸びて、彫刻のようだ。ウーロン茶を飲んで小休止していた太田先輩も復活し、「よーし、俺も」と息巻いている。
じゃあ…とパンツを履こうとすると、塩崎先輩に手首を掴まれた。
「菅原君、まだいけるよね?」
「えっ、いやまあ…でも…」
「もっとたくさん欲しいの、ね?」
「いや、でも、俺は…」
男2人と目が合う。竹内君は黙って頷き、太田先輩は、「俺らでゴールデントライアングルだな!」なんて呑気なことを言っている。
塩崎先輩は、四つん這いになって俺らに尻を向けた。自分で尻の肉を掴み、ビショビショに濡れそぼった肉裂と小さな後ろの穴を広げてみせた。
「みんなで私のことめちゃくちゃにして…?」
悪魔みたいな女がうっすら微笑んでいた。俺は薄ら怖さと同時に、どうしようもない欲望がこみ上げ、再び下半身に血液が集まり始めていた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)