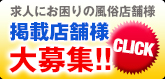365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第2話退屈な雨(後編)-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第2話】退屈な雨(後編)
唾液でべとべとになった亀頭を手でこねまわす。
舌を長く延ばして、男の顔を見ながら我慢汁を舌先でチロチロと舐め取る。男は眉間にしわを寄せ、切なげな声をあげた。
「あっ…そんな…」
竿に舌を這わせると、蒸れた男の臭いが鼻についた。大げさに鼻を鳴らして陰毛と陰茎の根元の臭いを嗅ぎながら、左手で自分の股間にそっと手を伸ばした。下着がぐっしょり濡れて愛液がしたたれ落ちそうだ。
(ああっ…この臭い、すごくいやらしい…)
肥大して敏感になったクリトリスを指先で刺激しながら、右手を根元に添えて亀頭を口ですっぽり咥えこんだ。口内で舌を絡ませながら少しずつ首を前後に動かす。男が「あーっ…」と小さく叫んだ。唾液を溜めてわざと音をたてる。じゅっ、じゅっという粘膜の卑猥な音が無人の非常階段に響いていた。男が苦しそうに喘ぐたびに、身体の芯がカッと熱くなり膣がヒクヒクして中からさらに液が溢れた。
(どうしよう、どんどん濡れてる…)
もっと喘ぎ声を聞きたくて、自然と動きが早くなる。男のペニスは破裂しそうなくらいパンパンに硬く膨れ上がっていた。男が息を荒くさせて何か言いたそうにしたので、眼だけで頷いた。
「も、ダメだ…出る…っ」
勢いよく精子が噴出し、竿がびくんびくんと何度も波打った。それらを全て受け止め、後から出る残りの精子も舐め取った。あまりにも量が多くて唇の端から少しこぼれ落ちたが、口内に溜まった唾液と精子を飲み干した。
「ハァッ…美味しい…」
視線がいつもよりだらしなくトロンとしてしまう。スカートの裾をたくしあげ、ぐっしょり濡れたパンツを脱いで片足にひっかけた。
壁に片手をつき、腰を突き出す。もう片方の手で自分の尻の肉をぐいと掴んだ。
「見て…こんなに濡れちゃった…」
こんなことして、まるで変態みたいだ。恥ずかしいのに気持ちよくてやめられない。
「私のも舐めて…」
一瞬の間があって、かすかな衣擦れの音がした。急に生温かい舌が充血した肉を刺激したので、思いがけず大きな声が出た。
「はああっ…」
男は大きな両手で尻の肉をわし掴みにし、びしょ濡れの秘部を舐め回した。
「あっ…あっ…」
舌の先端でひだをなぞったり、強く吸ったりされると、気持ちよくて腰をくねらせてしまう。
「ああっ…いい…そこ…きもちいいっ…」
耐え切れなくなって上半身を起こし、上体をひねって後ろを向いた。
「お願い…このまま挿れて…」
男の唇とその周りがいやらしく濡れていた。目が鈍く鋭く光っていて、息は荒く、眉間に深いしわが寄っていて、獣みたいでドキドキした。
駅で会った時とはまるで別人のようだった。
張り詰めた亀頭を濡れた肉襞に何度も擦りつけられ、じれったくて淫らに腰をくねらせた。
「あっ…ん、早く来て…」
潤い過ぎた肉壁は、いきり立ったペニスをいとも簡単に受け入れてしまった。男が、苦しそうに「うっ…わ」と小さく叫んだ。
「中、すっごいトロトロになってる…」
腰を引き、亀頭で敏感な入り口の肉を小刻みに刺激する。
「あっ、んんっ…いいっ…そこ、気持ちいい…」
しばらくの間、短いピストン運動を続けていたが、
「ダメだ…我慢できない…」
と呟くと、男は腰を両手で抱え力強く一気に奥まで突き上げた。
「んっああっ」
頭の芯がビリビリ痺れる。粘膜が擦れ、濡れた肉がぶつかり合う卑猥な音が余計にいやらしさを引き立てた。その音が次第に早くなるにつれて、下品なくらい腰を振った。
「ああっ…いい…っいいっ……すごいっ…」
「ごめ…、も…すぐイキそう…」
ズチュ、というぬかるんだ音が、一層激しくなる。いつのまにか右手で自らの肉芽をかき回していた。男の腰の動きに合わせて蜜に塗れた筋を中指で上下に刺激すると、身体がわなないて大きな波が押し寄せるのがわかった。
「あっ…あっ…もうイク…イクっ…!」
「…出るっ」
「あああっ」
男は素早く膣からペニスを抜き、地面に向かって放出した。
足元に白濁液が飛び散る。2度目の射精とは思えない量だった。
2人の呼吸は荒く熱っぽかった。
背後の男は放心した様子で、愛液と精液でベトベトになったペニスをぶら下げている。薄汚れたコンクリートの壁にもたれながら、甘く疼く悦びの余韻に浸った。
なんでこんなに楽しいのだろう。
口に咥えるのも舐めてもらうのも挿入でさえも、今までは相手が望むから、喜ぶからしていただけなのに。
向き直って小さくキスをすると、男の方から舌を絡めてきた。自分の愛液の味がする。耳元で「すごく気持ちよかった…」と、うっとり呟いた。本心だった。
「俺も…ていうか、いや、こんなん初めてで…」
男が足首まで落ちていた下着とズボンを慌てて引き上げたので、思わずフフッと声を出して笑った。
「あっ可愛い」
と、急に顔を覗き込まれた。
「今日初めてちゃんと笑いましたね」
そういえば、そうかも。なんだか照れ臭くて、顔が赤いのがバレないように男の首筋に小さく口づける。
「ねえ、もう少しゆっくりできる場所にいきませんか?」
と、耳元で囁いた。
「…もっと欲しいの」
挑戦的な笑みを浮かべると、男もつられて「望むところです」と笑った。
雨雲はもうどこにも見えなかった。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)