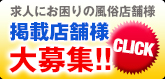365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第16話レモンサワー (後編)-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第16話】レモンサワー (後編)
女将さんは僕に背を向けると、スカートを捲り上げ、大きく熟れたお尻を突き出して物欲しげに腰を振った。
「滝沢さん、お願い、すぐにハメて…」
「えっ、いや、まだ何にも…!」
「ううん、だって、もうグショグショなのよ」
そう言ってレースのパンツを自分でずらすと、分厚い肉襞の間からすでに蜜が溢れ出て、クロッチにねっとりと糸を引いていた。
(マジかよ、この人もしかして超淫乱なんじゃ…)
てらてらと光る割れ目に中指をゆっくり沈み込ませてみると、中は既に熱くひくついていた。
「はあっ…ん!」
指を曲げて内側の肉壁を指の腹でなぞると、女将さんは上半身を弓なりにし、すすり泣くようによがった。
「ああっ…いや、滝沢さん、指だけじゃいやなの…」
「でも、い、いいんですか…ほんとに」
「いいの…お願い、私のこと犯して…」
両手で自分の臀部を鷲掴みにし、恥肉をだらしなく広げて懇願する熟女の姿は卑猥そのものだった。
僕は小さく「くそっ」と吐き捨てると、急いでベルトを外し、硬く張り詰めた肉塊を女将さんの濡れた割れ目に一気に突き立てた。
「ああーっ…いいっ、いいっ!」
のそげって叫ぶその声があまりに大きいので、僕は慌てて女将さんの口に指を挿れた。
女将さんは僕の指に長い舌を絡ませながら、激しく腰を振った。
女将さんのくぐもった喘ぎ声と、下腹部と臀部の肉がぶつかり合う音が有線の演歌をかき消していた。
女将さんは涙目で首を捻り、僕に何かを訴えてきた。
「ハァッ…滝沢さん、あの、叩いて…欲しいの」
「ええっ?」
「お尻を、叩いて…」
「お、お尻ですか」
遠慮がちに臀肉をパシンと叩いてみると、女将さんは恥ずかしそうに「ううん、もっと強くして」と腰をくねらせた。
(ええいままよ!)
思い切りピシャリとはたくと、女将さんは全身をぶるっと震わせて「はああん…っ」と甲高い声をあげた。
「ああんっ、あんっあっ、気持ちいい…っ」
次第に赤く腫れ上がっていく女将さんの尻を見て僕は妙に興奮した。
強く叩く度に柔肉がギュッと絡みついてくる。
「うわっ、女将さん、僕ちょっと…長く持たないかもしれませんっ…」
僕は射精のことしか考えられなくなってきて、女将さんの腰を両手で掴み、奥の子宮口めがけてガツガツと根元まで攻めた。
カウンターに寄りかかって尻を突き出し髪を振り乱してよがる彼女の姿は獣のようだった。
「ああっすごいっ、そこ…そのまましてえっ」
「あーっ気持ちいい、女将さんすごい気持ちいいです」
「イキそうっ、あっイクッ、イクッ…そのまま突いてぇ」
「ああ、ダメだ、僕もう…っ」
「あっ来る…っ、すごいの来るっ! あーイクッイクッ…イクーッッ」
「ううっ…!」
女将さんの身体が大きく波打つのを確認してから、僕は彼女の大きなお尻に熱い精液をぶちまけた。
その後、僕の家に移動してもう一回、朝起きてから更にもう一回してしまった。
女将さんは年上とは思えないほど貪欲で、僕は体中の体液を絞りとられてしまった。
「あら、いらっしゃいませ」
片岡さんに誘われて再びおでん屋に足を運んだ。今日は少し混んでいて、女将さんはカウンターの中で忙しなく動いていた。相変わらず美しかった。
仕事の話で熱くなっていると、メールの着信があった。女将さんからだった。
『今日もたくさんしてくれるんでしょう?』
顔を上げると、カウンターの中で淫乱の目をした女将さんが小さく微笑んでいた。
「くそーたまんねえな」とひとりごちると、片岡さんが
「そうだねえ、たまらんねえ」
と笑顔で相槌を打った。きっとレモンサワーのことを言っているのだろう。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)