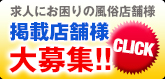365日マネー女子宣言!(サンロクゴ)の官能小説~女子的夜話~-第31話「陰と陽」前編-
風俗求人の無料掲載官能小説~女子的夜話~

【第31話】「陰と陽」前編
いつもは必ず断っていた二次会のカラオケに、強制参加させられた。
社員の先輩に「今日女性少ないからお願い!」と手を引っ張られ、断る余地がなかった。
私のような陰気臭い女がいては、場の空気が悪くなってしまうのではないかと危惧したが、カラオケは無事に盛り上がった。
私はドリンクの注文係に徹し、なんとか数時間をやり過ごした。
深夜1時近くにやっと解散となり、三次会へ向かう男性数名以外は、数台のタクシーに分かれた。
個人タクシーに乗り込み、運転手に行き先を告げると、営業部の大島課長が、
「あっ、そのタクシー板橋方面? 俺も乗せて!」と叫んで、座席に滑り込んできた。
「ごめんごめん、牧野ちゃんも同じ方向だって聞いたから」
大島課長は明るく笑った。課長はノリが良く仕事もできるので社内で人気者だ。
私のような地味な派遣の事務員は、遠くから眺めるだけで話す機会もなかった。
「珍しいね、牧野ちゃんがこんな時間までいるなんて。いつも一次会で帰っちゃうよね」
「あっ、は、はい、カラオケ、苦手なんで」
「そっかー。でもえらいよね。みんなのドリンクに気を配って注文してくれて」
見られてたんだ。と思うと顔がカッと熱くなる。
しかし、気配りしていたのは私よりもむしろ大島課長の方で、盛り上げたりビールをついだりしてほとんど動き回っていた。
「カラオケ苦痛じゃなかった? 遅くまで付き合わせちゃってなんか悪かったね」
顔を覗きこまれ、ますます挙動不審になる。
優しいし顔もいい。さぞモテるのだろう。
女性社員から「遊びで付き合うなら大島さんがいい」と人気な一方、「結婚したら浮気しそう」とも評されている。
明治通りを北に進み、大きな交差点に差し掛かるころ、大島課長が窓の外を見ながらふいに呟いた。
「俺、やっぱり池袋で降りようかな」
理由を聞いていいのか分からずチラと覗き見すると、課長はそれに気づいて苦笑した。
「あ、なんか飲み足んないから、ちょっと飲んでから帰ろうと思ってさ」
「……」
私も行きたい、と喉まで出かかったが言えなかった。
飲み足りないというのは口実で、
実は私と同じタクシーに乗っているのが耐えられないだけかもしれないからだ。
「もし時間まだ大丈夫なら、牧野ちゃんも一緒に飲む?」
「えっ」
思いがけない言葉に、体が固まった。「私なんかでよければ」の一言が、詰まってしまってなかなか言えなかった。
その後、雰囲気のいいダイニングバーで乾杯をして、よく笑いよく話したのは覚えている。
しかし、何を話したかのか、どのくらい飲んだのか、いつどうやって移動したのかも分からない。
ひどい二日酔いも、記憶をなくすまで泥酔したのも初めてだった。
さらに言うなら、目が覚めたとき隣で男が寝ていたのも、生まれて初めてだった。
横で寝息を立てているのは、紛れもなく大島課長だ。
ラブホテルの床に、私と課長の服が散乱していた。私は全身の血の気が引いていくのを感じた。
この状況は何だ。
とにかく服を着なければと布団から飛び出そうとすると、寝ていたはずの大島課長が私の腕を掴んだ。
寝ぼけた様子で「おはよう」と言うと、そのまま腕をグイと引っ張って抱き寄せ、私の胸に顔を埋めた。
目を閉じたまま、赤ん坊のように私の乳房に吸い付いた。
「やっ、お、大島さん、あのっ」
柔らかな唇で乳頭を刺激されるのがくすぐったくて、身をよじらせた。
大島課長は両手で乳房を揉んだり、軽く指先でつまんだりしながら、勃起した乳首を優しく舐め続けた。
もともと男性経験が少なく、前戯の短い人ばかりだったので、こんな風に乳房を長く攻められるのは初めてだった。
「ああっ、待って、そんなにそこばっかり舐めちゃ」
私の声が甘くなると、大島課長の目が開き、悪戯っぽく笑った。
「ゆうべは自分から舐めてって言ってたよ。ここ好きなんでしょう?」
「え、嘘…そんなこと」
言うはずがない。でも、確かに身体は恥ずかしいくらいにビクビクと反応し、高まっていた。
私は腰を浮かし、自分の陰毛に手を伸ばしていた。

藍川じゅん
元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中。
バックナンバー
-
 【第93話】女王様ごっこ その2
【第93話】女王様ごっこ その2
-
 【第92話】女王様ごっこ その1
【第92話】女王様ごっこ その1
-
 【第91話】精子の味 その2
【第91話】精子の味 その2
-
 【第90話】精子の味 その1
【第90話】精子の味 その1
-
 【第89話】避暑地 その2
【第89話】避暑地 その2
-
 【第88話】避暑地 その1
【第88話】避暑地 その1
-
 【第87話】言葉責め 2
【第87話】言葉責め 2
-
 【第86話】言葉責め 1
【第86話】言葉責め 1
-
 【第85話】昼呑み 2
【第85話】昼呑み 2
-
 【第84話】昼呑み 1
【第84話】昼呑み 1
-
 【第83話】カーセックス 2
【第83話】カーセックス 2
-
 【第82話】カーセックス 1
【第82話】カーセックス 1
-
 【第81話】パイパン その2
【第81話】パイパン その2
-
 【第80話】パイパン その1
【第80話】パイパン その1
-
 【第79話】スパンキング その2
【第79話】スパンキング その2
-
 【第78話】スパンキング その1
【第78話】スパンキング その1
-
 【第77話】赤い縄の誘惑 その2
【第77話】赤い縄の誘惑 その2
-
 【第76話】赤い縄の誘惑 その1
【第76話】赤い縄の誘惑 その1
-
 【第75話】「おしり初体験 その2」
【第75話】「おしり初体験 その2」
-
 【第74話】「おしり初体験 その1」
【第74話】「おしり初体験 その1」
-
 【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
【第73話】「プチ露出 プチ青姦 その2」
-
 【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
【第72話】「プチ露出 プチ青姦 その1」
-
 【第71話】「宅呑み(2)」
【第71話】「宅呑み(2)」
-
 【第70話】「宅呑み(1)」
【第70話】「宅呑み(1)」
-
 【第69話】「レッスン2」
【第69話】「レッスン2」
-
 【第68話】「レッスン1」
【第68話】「レッスン1」
-
 【第67話】「金縛り」
【第67話】「金縛り」
-
 【第66話】「押入れ」エピローグ
【第66話】「押入れ」エピローグ
-
 【第65話】「押入れ」後編
【第65話】「押入れ」後編
-
 【第64話】「押入れ」中編
【第64話】「押入れ」中編
-
 【第63話】「押入れ」
【第63話】「押入れ」
-
 【第62話】「スロウ」後編
【第62話】「スロウ」後編
-
 【第61話】「スロウ」前編
【第61話】「スロウ」前編
-
 【第60話】「アプリ」エピローグ
【第60話】「アプリ」エピローグ
-
 【第59話】「アプリ」その3
【第59話】「アプリ」その3
-
 【第58話】「アプリ」中編
【第58話】「アプリ」中編
-
 【第57話】「アプリ」前編
【第57話】「アプリ」前編
-
 【第56話】「鍋」後編
【第56話】「鍋」後編
-
 【第55話】「鍋」中編
【第55話】「鍋」中編
-
 【第54話】「鍋」前編
【第54話】「鍋」前編
-
 【第53話】「ゼロのキス」後編
【第53話】「ゼロのキス」後編
-
 【第52話】「ゼロのキス」中編
【第52話】「ゼロのキス」中編
-
 【第51話】「ゼロのキス」前編
【第51話】「ゼロのキス」前編
-
 【第50話】「オフィス」後編
【第50話】「オフィス」後編
-
 【第49話】「オフィス」前編
【第49話】「オフィス」前編
-
 【第48話】「お兄ちゃん」後編
【第48話】「お兄ちゃん」後編
-
 【第47話】「お兄ちゃん」前編
【第47話】「お兄ちゃん」前編
-
 【第46話】「お見舞い」後編
【第46話】「お見舞い」後編
-
 【第45話】「お見舞い」前編
【第45話】「お見舞い」前編
-
 【第44話】「家政婦」後編
【第44話】「家政婦」後編
-
 【第43話】「家政婦」前編
【第43話】「家政婦」前編
-
 【第42話】「カウンター」後編
【第42話】「カウンター」後編
-
 【第41話】「カウンター」前編
【第41話】「カウンター」前編
-
 【第40話】「バス」後編
【第40話】「バス」後編
-
 【第39話】「バス」前編
【第39話】「バス」前編
-
 【第38話】「幼馴染」後編
【第38話】「幼馴染」後編
-
 【第37話】「幼馴染」前編
【第37話】「幼馴染」前編
-
 【第36話】「蛙」後編
【第36話】「蛙」後編
-
 【第35話】「蛙」前編
【第35話】「蛙」前編
-
 【第34話】「隣人」後編
【第34話】「隣人」後編
-
 【第33話】「隣人」前編
【第33話】「隣人」前編
-
 【第32話】「陰と陽」後編
【第32話】「陰と陽」後編
-
 【第31話】「陰と陽」前編
【第31話】「陰と陽」前編
-
 【第30話】「女の子願望」エピローグ
【第30話】「女の子願望」エピローグ
-
 【第29話】「女の子願望」後編
【第29話】「女の子願望」後編
-
 【第28話】「女の子願望」中編
【第28話】「女の子願望」中編
-
 【第27話】女の子願望 (前編)
【第27話】女の子願望 (前編)
-
 【第26話】マチコ先生の性教育1
【第26話】マチコ先生の性教育1
-
 【第25話】雷雨 (後編)
【第25話】雷雨 (後編)
-
 【第24話】雷雨 (中編)
【第24話】雷雨 (中編)
-
 【第23話】雷雨 (前編)
【第23話】雷雨 (前編)
-
 【第22話】家庭教師 (後編)
【第22話】家庭教師 (後編)
-
 【第21話】家庭教師 (前編)
【第21話】家庭教師 (前編)
-
 【第20話】美しい人 (後編)
【第20話】美しい人 (後編)
-
 【第19話】美しい人 (前編)
【第19話】美しい人 (前編)
-
 【第18話】女子トイレ (後編)
【第18話】女子トイレ (後編)
-
 【第17話】女子トイレ (前編)
【第17話】女子トイレ (前編)
-
 【第16話】レモンサワー (後編)
【第16話】レモンサワー (後編)
-
 【第15話】レモンサワー (前編)
【第15話】レモンサワー (前編)
-
 【第14話】整体院 (後編)
【第14話】整体院 (後編)
-
 【第13話】整体院 (前編)
【第13話】整体院 (前編)
-
 【第12話】ひとつ屋根 (後編)
【第12話】ひとつ屋根 (後編)
-
 【第11話】ひとつ屋根 (前編)
【第11話】ひとつ屋根 (前編)
-
 【第10話】大人の手 (後編)
【第10話】大人の手 (後編)
-
 【第9話】大人の手 (前編)
【第9話】大人の手 (前編)
-
 【第8話】秘密の診察室 (後編)
【第8話】秘密の診察室 (後編)
-
 【第7話】秘密の診察室(前編)
【第7話】秘密の診察室(前編)
-
 【第6話】放課後(後編)
【第6話】放課後(後編)
-
 【第5話】放課後(前編)
【第5話】放課後(前編)
-
 【第4話】口からでまかせ(後編)
【第4話】口からでまかせ(後編)
-
 【第3話】口からでまかせ(前編)
【第3話】口からでまかせ(前編)
-
 【第2話】退屈な雨(後編)
【第2話】退屈な雨(後編)
-
 【第1話】退屈な雨(前編)
【第1話】退屈な雨(前編)